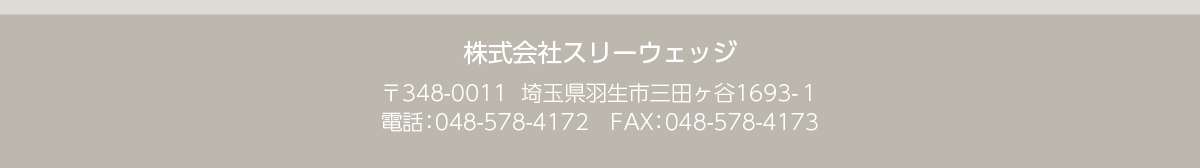犬のおかげ
前々回、「ハリケーン・レイ」で、迂闊にも「神」とか「愛」という言葉を使ってしまった。「レイ」に対する止め処もない想いで少し気持ちが昂ぶっていたのかも知れない。私は、かねがね犬や猫たちは「神」であると言ってはばからない。
ところが「愛」となると、何となくピンと来ないものを感じてしまう。
私にとって「神」というのは、本居宣長の歌にある
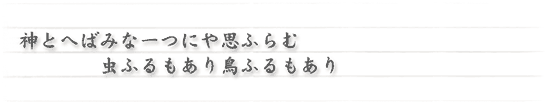
とういうことで、虫も鳥も、そして犬も猫たちも「神」、つまり八百万(ヤオヨロズ)の「自然神」という認識であってキリスト教で言うところの「GOD」ではない。
したがって、「愛」も「LOVE」ではなく、自然の生命に対する畏敬の念からくる心情のようなものであり、私の場合「GOD IS LOVE」は「自然は神である」という解釈になる。
しばらく前、青山のわくわくハウスというスペースで生食のセミナーをやっていた時のこと、トレーナーのKさんが、トレーニングの基本は「愛」だと言い、私たち飼い主を愛している犬たちには愛で応えなければならない、というようなことを言った。
そこで私は、われわれは犬たちを愛しているかもしれないけれど、犬たちは私たちを愛しているわけではない、と年甲斐もなく「愛」という言葉に引っ掛かり思わず反論してしまったことがある。
「愛」を、国語辞典で解釈すると、「個人の立場や利害にとらわれず、広く身の回りのものすべてに存在価値を認め、最大限に尊重して行きたいと願う、人間本来の暖かな心情」となるが、犬たちにそういう心情があるとは思えない。
また、ペット業界には余りにも安易で偽善的な臭いもする「愛」が氾濫していることに対して少なからず違和感をもっていることもあり、ついつい、そういう人ではない愛情深いトレーナーのKさんを悲しませてしまったことは反省しきりである。
ところで、人と人、男と女の「愛」という茫洋としたテーマについて語るつもりも資格もないのだが、人と犬や猫たちとの関係において氾濫している「愛」と言うキーワードの本質はどのようなものなのだろうか。
以前、このESSAYの「肉の恩返し」で書いたように、大昔、私たち人間の祖先は肉食動物の残飯を漁り肉食を覚えたことによって脳が発達した。
その発達した脳を駆使する事で、狩の武器を考え出し、家畜を飼い、火を発明したことで農耕を営み、そして何よりも「言葉」を授かり情報の共有が容易になったことでこの地球上の支配者になり得た。
ところが、昨今の人間社会を見渡したところ、まるでタガが外れてしまったかのような有様で、「言葉」は世を欺く道具に成り果ててしまったような体たらくである。
イヌ語が分かる、という人がいるが、研究不足のせいかかもしれないが私には分からない。ただ、犬たちが今、私に何を要求しているのかどうかについてはほとんど理解しているつもりであるし、犬たちもまた、私が何を言わんとしているのか理解しているものと感じている。
したがって、「言葉」を介さなくても、犬たちと一緒に暮らし、仕事をしていることになんら支障を感じることはない。
このような関係を「愛」という「言葉」で言い表していいものなのかどうかが私にはどうも合点がいかないのだ。

私は、日がな一日犬たちの、とりわけその眼に見入っている事がある。
そして、私が犬たちのその眼に語りかけるものは、タヒチの画家の言葉を借りるならば、
「我々はどこから来たのか? 我々は何ものなのか? 我々はどこへ行くのか?」
という命題についてである。
「私たち人間は、君たちに比べどうしてんなにも醜い動物に成り下がってしまったのだろうか……」
「君たちのその凛とした姿はなんと立派で魅力的なことか……」
「もしかするとわれわれ人間は、言葉なぞ授からなかった方が良かったのかもしれない」
私にとって、最も身近にいる「神」である犬たちは、取るに足らないようなこの身であろうとも、一体この先どのように生きるべきなのだろうか、その答えを言葉では教えてくれないけれど、そのような生命の重大な課題について思いを馳せる貴重な時間を与えてくれる存在である。

最近、その眼は、
「何をくよくよ考えているんだ。俺たちのように生きればいいではないか……」
そう言っているような気がしてならない。