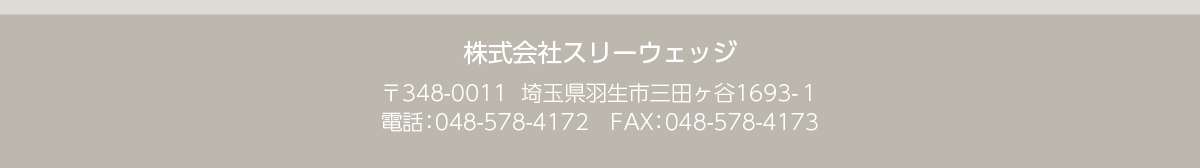犬や猫は、ペットを超えた
太宰治の未完の遺作「グッドバイ」の序文に、作者の言葉として次のように示されている。
唐詩選の五言絶句の中に、人生足別離の一句があり、私の或る先輩は、これを「サヨナラ」ダケガ人生ダ、と訳した。まこと相逢ったときのよろこびは、つかの間に消えるものだけれども、別離の傷心は深く、私たちは常に惜別の情の中に生きているといっても過言ではあるまい。
「グッドバイ」は、男と女の別れ話のオムニバスだが、その制作の渦中、自らも女性と心中をして果てた。
また、寺山修司は、
「さよならだけが人生ならば また来る春はなんだろう…… さよならだけが人生ならば 人生なんていりません」
などという少女めいた詩を作った。
「さよならだけが人生だ」という訳詩をしたのは井伏鱒二で、本来の意味は、「すぐに別れは来るものだけれど、酒を飲み交わしながら今この時を大切にしよう」という一期一会のような意味合いのことなのだが、それではありきたりの話になってしまう。
太宰や寺山が反応した「さよならだけが人生だ」というニヒルで鮮烈なフレーズは、訳意を超えて凄みを持った名言として世に残ることになったのだ。
無頼を粋がっていた私などの若造時代も、酒をあおってはこのフレーズを夜な夜な念仏のように唱えていた。
いまどき、とりわけ若い年代の人たちと酒を飲んで、「人生とは…」などと口走れば、途端に「ウザイ!」と嫌われるに相場が決まっている。
そうだとしたら、酒を飲んで人生を語らずして、一体何を語り合うのだろう。
ところで、その太宰の作品に「蓄犬談」というユーモア溢れる短編小説がある。
……私は、犬をきらいなのである。早くからその狂暴の猛獣性を看破し、こころよからず思っているのである。たかだか日に一度や二度の残飯の投与にあずからんがために、友を売り、妻を離別し、おのれの身ひとつ、家の軒下に横たえ、忠義顔して、かつての友に吠え、兄弟、父母をも、けろりと忘却し、ただひたすらに飼主の顔色を伺い、阿諛(あゆ)追従(ついしょう)てんとして恥じず、ぶたれても、きゃんといい尻尾(しっぽ)まいて閉口してみせて、家人を笑わせ、その精神の卑劣、醜怪、犬畜生とはよくもいった。日に十里を楽々と走破しうる健脚を有し、獅子をも斃(たお)す白光鋭利の牙(きば)を持ちながら、懶惰(らんだ)無頼(ぶらい)の腐りはてたいやしい根性をはばからず発揮し、一片の矜持(きょうじ)なく、てもなく人間界に屈服し、隷属(れいぞく)し、同族互いに敵視して、顔つきあわせると吠えあい、噛みあい、もって人間の御機嫌をとり結ぼうと努めている。
私は、嘗て、これほどまでに犬に対し罵詈雑言を吐いた言葉を知らない。
ところが、これほどまでの犬嫌いが、散歩の折に野良の仔犬がついてきて、とうとう犬を飼う羽目になる。そうするうち家を越すことになるのだが、折りしも犬が皮膚病を罹ってしまい、犬をどうするか悩んだ末、薬殺するしかないと決め実行に移すことになる。
私は、途中で考えてきたことをそのまま言ってみた。
「弱者の友なんだ。芸術家にとって、これが出発で、また最高の目的なんだ。こんな単純なこと、僕は忘れていた。僕だけじゃない。みんなが、忘れているんだ。僕は、ポチを東京へ連れてゆこうと思うよ。友がもしポチの恰好(かっこう)を笑ったら、ぶん殴(なぐ)ってやる。卵あるかい?」 「ええ」家内は、浮かぬ顔をしていた。
「ポチにやれ、二つあるなら、二つやれ。おまえも我慢しろ。皮膚病なんてのは、すぐなおるよ」
引越しの事態に犬を薬殺しようとして果たせず、その挙句に訳のわからない理屈を言って、結局、あれほど嫌っていた犬を、甲府から引越し先の三鷹まで一緒に連れて行き、引き続き飼うことを決断するに至る。

ラブラドール飼育の奮戦記を描いた随筆、「尻尾のある星座」を書いた村田喜代子(芥川賞作家)も、犬の話を書くことに最初は躊躇したと言っているが、その後の村田は、今や犬話を知的に語る第一人者であり、動物実験反対の先頭を走ってもいる。
かくのごとく、よほどの理由がない限り多くの人は抗いがたくも犬に魅了される。
つまり、犬や猫という動物は、肉食動物でありながら、とうの昔からペットという範疇を超えて人社会の一員としての存在を確立していたのである。