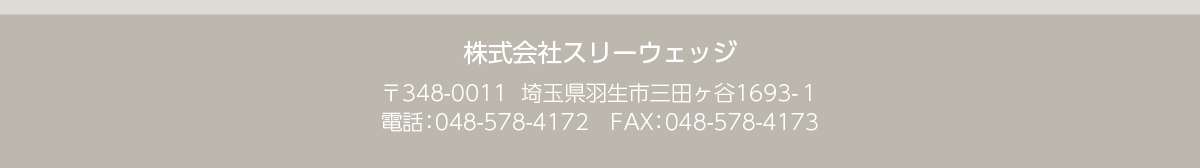10年経っても飼い主を忘れない
先日、以前コラムでとり上げた「ユリシーズの涙」をまたこのブログに書いてしまった。
ずいぶん焼きが回ったなぁと、少し落ち込んでしまったのだが、どうしてももう一度その愛読書のことを書かねばならなくなった。
「ユリシーズの涙」は、犬と人間にまつわるエピソードが43章からなるエッセイにつづられている。
その第一は、当然表題にあるユリシーズについてのエピソードである。
「ユリシーズ」とは、ホメーロスの「オデュッセイア」(英名・ユリシーズ)の主人公で、紀元前8世紀の作品と言われている。
そのユリシーズの中の挿話を「ユリシーズの涙」ではとりあげている。
国を追われたユリシーズが、復讐のため10年ぶりにボロ衣を纏い変装して故国に姿を現した。旧知の人々が誰一人見抜けない中、故国に残していった愛犬アルゴスだけが見抜いてしまい嬉しそうに尾を振った。それを見たユリシーズは、アルゴスに駈けよって抱きしめたい気持ちを抑えて、知らぬ振りをして通り過ぎた。
その辛さに涙した、その涙さえ誰にも悟られてはならなかった。
10年ぶりに飼い主に再会したアルゴスは、そんなユリシーズを見送った直後に静かに息を引き取った。
犬と暮らすということは、いろいろな理由によって否が応でも別れが待っている。
そんなことは言われなくも誰でも分かっていることだが、そこには触れないように目をそむけている。
そして、その別れの痛みは、それぞれの感性や価値観によって大いに異なると思う。
同時に、その痛みは本人以外に分からない。
何故なら、人間同士どころではない、その犬と飼い主との濃密な関係には、他者が窺い知ることなどできない深い物語があるのだから。