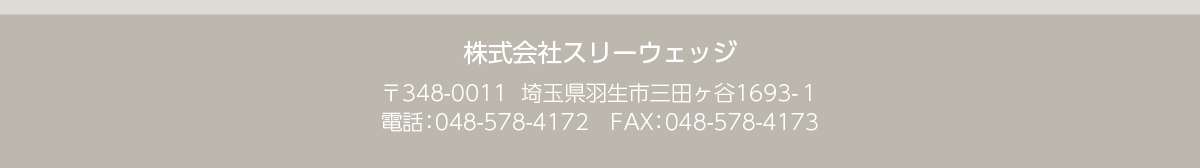珀の贈りもの
「珀」の出産予定日は11月3日だったが、11月1日午後11時35分に第一子、そして午前3時には7頭の子犬の出産を無事に終えた。この日が犬の日だということは、後日聞き知った。
スタッフブログに書いた通り、今回の「珀」の妊娠は、もとはと言えば私のちょっとした不注意が引き起こした、取り返しようのない失態だった。しかしこうなった以上、なによりも母子ともに健康に“出産”という大仕事を乗り越えてもらうことを願うより他はない。交配から二ヶ月、心の片隅に罪の意識を背負い込みつつも、栄養面で特別な飼養管理を心がけ、「珀」の無事を祈り続けてきた。
当日、出産間近かになって藁谷から連絡を受けたスタッフたちが、深夜にもかかわらず、事務所に仮設された産室に集まった。二子目の誕生時には全員が顔を揃えていた。
社長と私以外のスタッフたちにしてみれば、今回がもちろん初めての犬の出産体験とういことでもあり、また、日頃のかれらの「珀」との親密度からして、それぞれの思いは察してあまりある。
全員がかわるがわる産室を覗き込み、一頭生まれるたびに押し殺した声で歓声を挙げる。人一倍感激屋で、犬たちの甘やかし隊長である原田にいたっては、一子目でポロポロ泣きだし、七子目の頃には涙が枯れ果ててしまう有様だった。
「珀」をことのほか可愛がっていた社長が産室に入り、つきっきりで「珀」の分娩を助け、励まし続けた。そのかいもあってか、一子目時には生まれた子犬をくわえてオロオロしていた「珀」も、二子目からは母犬としての役目を見事に果たし続けた。
虎毛三頭、赤四頭—-すべてが無事に終わった。
スタッフ一同、感動さめやらぬ面持ちで、その場はさながら出産&誕生パーティーのような祝賀ムードに。いっぽう、産室が置かれた部屋は一階なのだが、二階にいる父犬の「虎次郎」は、生まれるごとに増える子犬の産声に反応し、吠えたり駆け回ったりして落ち着かない様子だった。
虎、お前の子犬だ!  明け方家に帰り、ようやく眠りについたころ、事務所に泊り込んでいた藁谷から電話が入った。
明け方家に帰り、ようやく眠りについたころ、事務所に泊り込んでいた藁谷から電話が入った。
「子犬が一頭危ないんです!鼻におっぱいが詰まったのかも!」
いつになく切羽詰った声だ。
「鼻を思いきり吸ってみてくれ!できるか?」
「はい!やってみます」
「それとお湯を沸かしておくんだ!すぐに行く」
タクシーを拾って駆けつけると、ほんの数時間前にみんなに祝福されて生まれたばかりの子犬は、母の「珀」 から離され、タオルにくるまれていた。
そして…そのときはまだすこし息があったが、間もなく息を引きとった。
「珀」の出産に立ち会うことで、生命誕生の神秘に触れ、歓喜したのもつかの間、その直後に向き合うことになってしまった「死」という現実。誰もが、その落差をどう受け止めていいものか途方に暮れ、うろたえていることがあきらかだった。
後から駆けつけた社長は、涙をこらえながらも、線香と花を手に小さな遺体を小箱に収め、霊園に電話をするべきか、それとも埋葬のほうがいいか、矢継ぎ早やに私を問いつめてきた。これまで何度となくこうした悲しみを乗り越えてきた社長ですら、心の動揺を隠しようもない様子だった。
逝ってしまった子犬の弔いの儀式を手厚くとり行うことで、悲しみを現実として受容し、その悲しみに区切りをつけなければならないと思ったのだろう。
しかし、そのときの私は、そんな社長の潔さにはとてもついていけない心境だった。
私の不注意に端を発したこれまでのいきさつに対し、自責の念に胸をえぐられるような痛みを感じながらも、私の頭には、死んだ子犬のことよりも、これから「珀」と子犬たちをどう育てていけばいいのかという思いが渦巻いていたのだ。それを万全になし終えなければ、私は自分の責務を全うすることができない。
起きてほしくないことは続くものなのか、次の日にも一頭の子犬が息を引き取った。
その遺体をどのように見送ったのか、今もって誰も私に語ろうとしない。
おそらく、最初の子犬の死に対する私の態度に疑問を持ったスタッフたちが相談してとった行動だろうと思う。たぶん、先に埋葬された兄弟犬と同じ場所にねんごろに埋葬され永遠の眠りについたに違いない。
そうあって欲しいと願うし、もしそうなら100CLUBのスタッフたちを、私は誇りに感じたいと思う。
日本で最高の愛犬家といえば、歌人でもある故・平岩米吉だと思うが、その平岩の詠んだ胸を打つ犬の歌がある。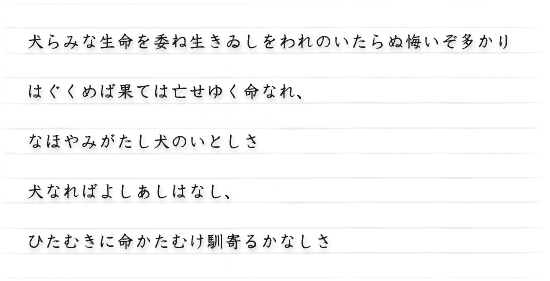 40年もの間、数多くの犬たちとともに暮らし、幾度となくその死に遭遇してきた者のみが知る境地ではなかろうか。
40年もの間、数多くの犬たちとともに暮らし、幾度となくその死に遭遇してきた者のみが知る境地ではなかろうか。
犬を愛し、ともに暮らすということは、いやおうなくその死期を看取ることになる。やりきれない悲しみと向き合うことになる。
それでも人は犬や猫たちを飼おうとする。
犬や猫たちがペットと化した社会には、「愛」という言葉が満ち溢れているが、そのいっぽうで「死」については、あたかもタブーであるかのように語られることが少ない。
しかし、生命あるものには避けようのない死が必ず待っている。そしてまた、死別の悲しみがあるからこそ、人は生きていることの喜びを再確認し、愛することの至福を享受することができるのだ。
それは、犬や猫たちを心から愛しともに暮らさなければ、実感できるものではない。 このたびの「珀」の出産がもたらしたもの—-。
このたびの「珀」の出産がもたらしたもの—-。
それは、そこにかかわった全員に、無私無限の愛というものがまぎれもなく存在することを教え、同時に深い絆をもたらした。
そのことは私たちに、これから犬や猫たちとどう付き合っていかなければならないのかという命題を、突きつけることにもなった。
それは、「珀」からの無言の贈り物だったのかもしれない。