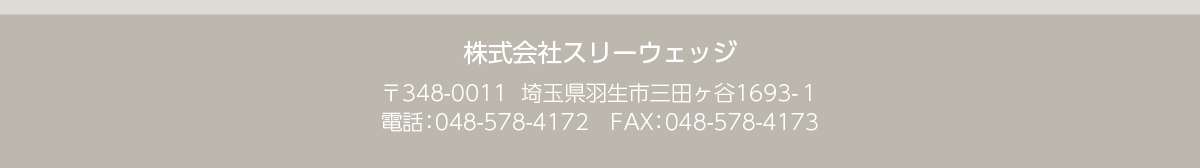回想の記 その2
敗戦後、映画、音楽、食品を始めとしてアメリカ文化が雪崩を打つように占領下の日本に押し寄せてきた。
アメリカナイゼーション、つまり日本のアメリカ化であり、戦後70年というのはまさしくそのような流れに染めつくされた。
ペットフードもその一例である。
一般的に、日本人は甚大な惨状を呈した敗戦を嘆き悲しんだのではなく、まばゆいばかりのアメリカ文化の到来を嬉々として受け入れたのだ。
平和の到来に歓喜し、戦後の復興という希望に満ちていた時代背景があったことも事実で、自分はそのような時代を71年間生きてきた。
アメリカ映画、そして音楽。ここではアメリカから入ってきた音楽の話をする。
小学生の頃、自分が最初に耳にしたのはカントリーウェスタンで、最も強烈な印象を受けたのはハンク・ウィリアムスだった。裏声を交えた独特な歌唱はその他の歌手から隔絶した個性をもっていた。
その音楽活動は、1953年29歳、薬物中毒で亡くなるまでの6年間という短いもので、多くの天才的な才能が夭折の人生を送る例に漏れず、流星のように現れて消えた。
その直後に現れた圧倒的な個性をもった歌手がエルビス・プレスリーで、カントリーウェスタンにブラックミュージックのリズム&ブルースを重ね合わせた、当時のアメリカの人種差別社会にあって革新的な音楽で、いわゆるロックンロールの誕生であった。
現在でも、エルビスの評価は歴代歌手の最高峰といわれている。
その影響を受けて、日本では有楽町の日本劇場(日劇)でロカビリーといわれた妙な音楽に熱狂した。
平尾昌晃、山下敬二郎、ミッキー・カーチスがロカビリー3人男といわれ大人気を博し、
舞台には無数の紙テープが投げられ歌い手はテープに埋まってしまって歌どころではない騒ぎだった。
そのような光景はTVで流されたことで記憶に残っているが、ほぼ同時期、私はジャズに出会ってしまった。
私の家の道を挟んだ向かいの菓子屋さんから、毎日、一日中大きな音でジャズが聞こえてきた。
隣のおもちゃ屋の親父さんが、「うるさいッ!」と、時々怒鳴り込んだこともあるほど大きな音だったが、私はその音楽に日を経つごとに引き込まれることになった。
私より12歳年上の菓子屋のAさんは、私がジャズキチになる先達となった。
Aさんが聴いていたオーディオは舶来ものだった。当時のレコードは78回転のSP盤で、片面で3分半位しか聴くことができなかった。
その頃、ベニー・グッドマンのカーネギーホール・コンサートでの「シング・シング・シング」は15分くらいの演奏だったもので、その1曲だけでSP盤のレコードが3枚必要だった。
当時は普通の家では手巻きの蓄音機でSP盤のレコードを聴いていたのだがAさんは舶来の電蓄(電気蓄音機)を持っていて、10枚位のSP盤をいっぺんにセットすると、自動的に順番に裏表がターンテーブルにセットされ針も自動でセットされる。
ジャズには耳を、電蓄には目を見張らせるものがあって、その瞬間アメリカって凄いなぁと、すっかりアメリカ文化にはまってしまったのだ。
その後、高校生になってから、Aさんに連れられて東京にジャズライブを欠かさず聴きに行くようになって、また、Aさんを通じて多くの名の知れた人たちに出会うことになった。