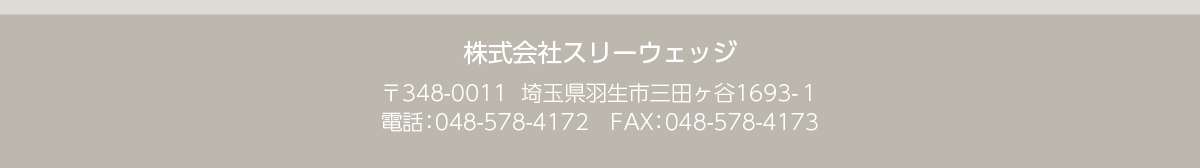ポール・ゴーギャンと犬
これまで腹にしまっておいた事を、どうしても話してしまわないと苦しくなってきたのでひんしゅくを恐れず話してしまうことにした。
それは2009年の夏の日のことだった。
国立近代美術館に「ポール・ゴーギャン展」を観に行った。
これまでゴーギャンの作品は何回も観ていたが、このときは遺書ともいわれ畢生の名作である「われわれは何処から来たのか われわれは何者か われわれはどこに行くのか」が展示されることに、居ても立っても居られない気持ちになっていた。
ところが私は身体障害者で、スーパーマーケットを押し車を使いながら一周するのが限界なくらい歩行が困難なのだ。もし会場が込んでいたらまともに絵の鑑賞などできないかも知れないとも思ったのだが、どうしてもこの絵だけは観ておかねばならないと意を決して出掛けることにした。
会場に着くと予想通りの混雑だったのだが、会場の入り口に車椅子が備えられていることに気が付いた。これは有難いと思い、障害者の手帳を提示して車椅子を使わせてもらうことにした。
車椅子を押すのは息子なのだが、息子も自分も、車椅子を押しなれていない者と乗りなれていない者なのだから、会場を廻るのに右往左往するところもあったのだが、ついに目当ての作品の前にたどり着いた。
自分の生涯、おそらく直接この作品に出会えるとは思ってもいなかった夢のような瞬間だった。作品の横幅は4メートル近くあり、縦は1・5メートルもある大作で、この作品を車椅子で観るには非常に不都合な位置取りにしかならず、どうしたものかとたじろいでいたのだが、親切な方がいらっしゃって作品のど真ん中に誘導された。
ところがそうなると、展覧会の目玉となる作品のど真ん中に位置取ってしまった車椅子が、大勢の鑑賞者にとってとんでもない邪魔な存在になること必定だ。
本心は、いつまででも立ち去りがたく作品に魅入っていたい。反面、他の鑑賞者を邪魔してはならないという済まない気持ちでもある。ところが、この混雑の最中、車椅子では思うような動きが取れず、結果的には2~30分もこの大作のど真ん中にいて、なんら思い残すことがない程くまなく鑑賞することが出来た。
腹にしまっておきたいと思ったのは、普段、障害者ということ自体、社会に対しとんでもない迷惑をお掛けしているという自覚をもっているのだが、その日の出来事は、障害者であることによって特別の恩恵を受けることになってしまったことに対する後ろめたさが消し難く残っていたからなのだ。これで少し気が楽になった。
ここで、ポール・ゴーギャンを語るつもりはないが、一つだけいうならばゴーギャンの作品には頻繁に犬が登場する。
そこにはゴーギャンの思想、死生観に根差した深い意味が込められているのだ。